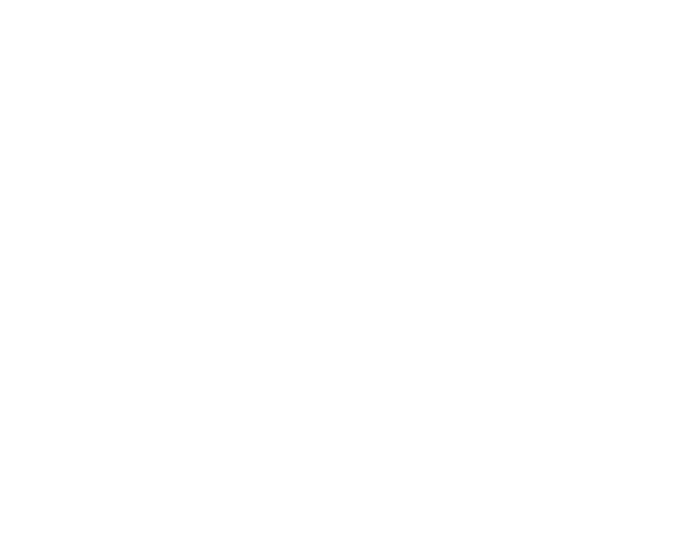もくじ
Toggleお子さんの発達が気になる親御さんへ
- 「子どもが落ち着いて座っていられない」
- 「こだわりが強く、些細なことで癇癪を起こしてしまう」
- 「他の子と比べて何か違う…」
こうした悩みを抱えていませんか?お子さんの特性に向き合いながらも、どうサポートすれば良いのか分からず、不安な日々を過ごしている親御さんは多いと思います。
そんな中、発達障がいの支援において高い効果が繰り返し証明されているのが ABA(応用行動分析) です。この記事では、ABAの基本的な考え方やその有効性、具体的なアプローチについて解説します。ぜひ最後までご覧いただき、「ゆあてらす」の取り組みに触れてください!
ABAとは?――科学的根拠に基づいた支援法
ABA(Applied Behavior Analysis)は、日本語で「応用行動分析」と訳されます。
行動が増えたり減ったりする仕組みを科学的に解明し、その原理を活用してお子さんの成長を支援する方法です。
アメリカなどでは発達障害への標準的な療法として広く普及しており、保険適用も認められています。具体的には、以下のような効果が示されています。
- 言語能力の向上
- 社会性の向上
- 適応行動の改善
特に自閉症幼児への早期療育として注目を集め、その後は障がいを持つ人々への一生涯の支援法として広がりを見せています。
ABAの基本原理――行動を観察し、良い行動を増やす仕組み
ABAでは、行動が生まれる流れを「行動前」「行動」「行動後」の3つに分けて考えます。
この3つを観察し、どのような対応が必要かを考えるのが基本的な流れです。
具体例:リンゴを手に入れる行動
- 行動前の出来事:「冷蔵庫にリンゴがあるのを見つけた」
- 行動:「親の手を引っ張って冷蔵庫に連れて行く」
- 行動後の結果:「リンゴをもらえた」
この流れを繰り返すことで、「親の手を引っ張る」という行動が強化されます。
行動の後に良い結果が得られると、その行動が増える――この仕組みを 「強化」 と呼びます。
ABAでは、この「強化」を活用して、言葉や社会性、自立のスキルを一つひとつ教えていきます。
困った行動を減らすために――「消去」の考え方
一方で、困った行動を減らす際には「消去」の考え方を使います。
例えば、買い物中にお菓子をねだって大泣きするお子さんがいた場合、
もし毎回お菓子を買い与えてしまうと、「泣けばお菓子がもらえる」という行動が強化されます。
しかし、「お菓子を買わない」という対応を続けた場合、その行動は次第に減少していきます。
このように、「良いことが起きない」ことを繰り返すことで、困った行動を自然と減らしていくのです。
ABAを使ってできること
ABAは、発達障がい特有の特性に対して、様々なアプローチを提供します。以下はその一例です。
1. 社会性の向上
他人の表情や感情を理解することが難しい場合、「貸して」「順番を守る」など、具体的な言葉や行動を教えます。
これにより、適切なコミュニケーションが取れるようになり、人との関わり方を学べます。
2. 興味の幅を広げる
一つの物に執着したり、特定の動きを繰り返す場合、遊び方や活動の幅を広げることで「生きやすさ」をサポートします。
3. 自傷や他害行動の改善
言葉で自分の気持ちを伝えることが難しい場合、ABAを通じてコミュニケーション能力を高めることで、望ましくない行動を減らします。
「ゆあてらす」ではABAを繰り返し学び、実践しています
「ゆあてらす」の職員は全員がABAの専門知識を持ち、日々研修を受けながらスキルを磨いています。
ただ理論を学ぶだけでなく、実際にプログラムに落とし込み、お子さん一人ひとりの特性や目標に合わせた療育を提供しています。
ゆあてらすが目指すもの
「成功体験」を積み重ねる支援
小さな成功を一つずつ積み上げ、お子さんが自信を持てるようサポートします。社会性と自立を育む具体的なゴール
入学後に必要なスキルを優先し、学校生活や日常生活でスムーズに適応できるよう支援します。卒業後も続くつながり
ゆあてらすでは、卒業後も安心して相談できるコミュニティを提供し、子どもたちが将来にわたって支え合える仲間を作るお手伝いをします。
今だからこそ始められる、未来への一歩
「ABAって良さそう」「子どもに合いそう」と感じていただけましたか?
今が行動を始めるタイミングです。
「ゆあてらす」で、お子さんの未来を一緒に描いてみませんか?
まずはお気軽にお問い合わせいただき、施設の見学にお越しください!